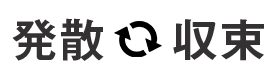表現のこと 「考える人 村上春樹ロングインタビュー」より
大学の授業では、さまざまな課題がではじめました。
Photoshop、白黒プリント、カラープリント、象徴とは、プロジェクト・ストリートファッションなどなど。
テーマが与えられている間は、楽なんです。
もちろん、それを乗り越えていく知恵と体力は必要かもしれません。でも、いちばん大変なのって追求するテーマを自分で見つけることと、それを掘り下げていくことです。
それについて考え始めると、1年に満たない程度のコースワークで何ができるのだろうか、と浮き足立ってしまいます。やれ、次の年のVISAはどうしようと か、進学どうしようとか。それらは小手先のことばかりです。それと、もともとが社会科学的な背景をもっているからか、経験的なアプローチ(過去の事例から 方向性を推定する)を重視してしまいがちです。
確かに、それも大切な僕の資産です。でも、それにとどまらないために進んできた道です。
自分が今やらなければならないのは、
スキルについては大学に任せながら、見る・収める(撮る・書く)ということについて考えを深めてフォーカスの精度をあげること。
創作についてのあれこれについては、以前読んだ「考える人 村上春樹ロングインタビュー」や「夢を見るために毎朝僕は目覚めるのです」に何重にも言及がありました。

この二冊については、インタビューだからさっと読み飛ばせるようで、実際にそれを身をもってわかるという段階に至るには、何度も読み返しつつ、自分にとっ てはこれは何に当たるのか、具体的な思考や行動に置き換える作業が必要です。そんなことはなかなかすぐにはできませんでしたから、数回読んでいるうちに、 気になったところには印をつけてあります。
今回は、テーマへの迫り方やそのあらわし方について、いくらか復習してみたいと思います。
「物語を掘り出す」36ページ
はじめは自分のなかにドラマや物語性はないと思っていたから、何かありそうな場所を選んで、とにかく足もとを黙々と掘って いくしかなかった。それを続けているうちに、足腰が強くなって、物語をより多くより長く引っ張り出せるようになりました。その物語というのは、結局のとこ ろ、自分の根っこから出てきているものです。
その根っこを表に引きずりだすというのは、ある場合には僕自身にとって非常にきついことでもあります。見たくないものを見なくてはならない、ということもあります。そういう作業に耐えるためには、文体を強固にしていくことが何より大事になってきます。
何かありそうな場所。これはありますね。いくつか抱えてこの地にやってきたのでぼんやりさせたまま放置するのではなく、黙々と掘ってみます。
ただ、ある程度時間がかかることは覚悟しねければならない。単純に図書館で本を読みすすめることもそうですし、実際にその地に立って見ること、滞在してみ ること、意見を交換してみること、写真や文章にしてみて反応を得ることですね。特に、自分や同年代に引きつけてみて、丹念に粘り強く掘るしか近道はないの だと思います。
新しい情報が次々とふってくる毎日なので、どこを掘ってたんだっけ・・・となってしまいがちだったのですが、ちょっと穴をたどって丁寧にやってみます。 (学生時代から恩師に、選びとったことを丁寧に確実にやるのが近道と言われていました。ぼくは進みが遅いくせに広げすぎるから。)
パラフレーズすること 47ページ
謎があるから解答がある、質問があるから答えがあるというものではない、ということです。これが謎です、これが答 えです。これが質問です、これが解答です。それをやってしまうと、物語ではなく、ステートメントになってしまいます。そんなの原稿用紙三枚くらいで終わっ てしまう。それができないから、三年ほどかけて、骨身を削って小説を書いているわけです。だからほんとに頭の良い人は、小説なんて書きません。こんな効率 の悪いことは、とてもやっていられないから。
小説というのは、もともとが置き換えの作業なのです。心的イメージを、物語のかたちに置き換えていく。その置き換えは、ある場合には謎めいています。繋が り具合がよくわからないところもあります。しかしもしその物語が読者の腹にこたえるなら、それはちゃんとどこかで繋がっているということです。
そういう「よくわからんけど機能している」ブラックボックスが、つまりは小説的な謎ということになります。そしてそのブラックボックスこそが、小説のライ フラインなんです。読者はある程度そのブラックボックスを、よくわからないなりに、自分の身のうちに抱え込まなくてはなりません。そしてできることなら、 そのよくわからない性を、自分なりの「よくわからない性」にモディファイしなくてはならない。もし真剣に自律的に読書をしようと思えば、ということです が。
ここの部分は、このインタビューを読んでいて、もっともしっくりきた部分です。
創作が、論文やステートメントとは違うのは、届け方をいかようにでもアレンジできるということじゃないでしょうか。もちろん、油絵とかダンスとか一定のルールはその分野にはあるでしょうけれど。
置き換えをしていくには、その置き換えするための抽斗をどれだけ持てているかや、置き換えのタイミングに気がつけるかというセンスも問われるでしょう。
このパラフレーズの置き換えについていけなすぎると、「この作品は一体??」「アートならなんでも許されるのか」という感想につながってしまう場合があります。もっとも、そこは創り手がどこまで届けたいと思うかにもよるのでしょう。
優れた小説家の作品は、どんな読み手でもある程度楽しめる気がします。
恋愛小説として深く感動を得られたという人もいれば、恋愛小説の衣をまとった別のテーマ設定に気がつく人もいる。作者に意図はあるにせよ、別に正解はない わけで、それぞれが楽しめる。ただし、そのパラフレーズのつながりを何段階渡っていけるか、で物語の本質的なメッセージに辿りつける可能性が高まります。 そこは、読者にも問われる点です。
写真にしても、パラフレーズという概念は重要な要素ではないかと思います。
設定したテーマを繰り返し繰り返し違う角度から光をあてて、写しとってみること。これは、まずは自分でやっていくしかないですね。
この雑誌のインタビューは、かなり濃密な内容を持っているので、次は描写についてや時間についても読み返して考えてみようと思います。
PS
この雑誌が出たときに、インタビュアーすごい!とTwitterでつぶやいたら、ジュンク堂のTwitterが「このインタビュアーは星野道夫さんの担当編集でもあったんですよ」と教えてくれました。つながる世界観ってあるんですね。
関連記事
-

-
スポーツにおける観察と洞察力から学ぶ
欧州やインドにいたときは、サッカーばかり見ていたが、日本ではやっぱり野球を見る機会が増える。
-

-
「アートのお仕事図鑑」美術手帖。アートやデザインの思考法は、広く求められている。
先日、TBSラジオ「ジェーン・スーの相談は踊る」を聞いていたら、リスナーからの相談メールで「
-

-
「写真の露出ハンドブック」
誰もが簡単に写真を写せる今だからこそ、じっくり考えてみたい写真の基礎知識。露出とはいったい何か?そん
-

-
よき生産者になるためには、よき消費者であれ
20代のころに読んだ本に書いてあった言葉である。 確か、読書家で有名な立花隆さんの本に書かれて
-

-
「豊かさの栄養学 」丸元淑生を読んで、食生活について考えた
毎日繰り返していることなのに、それほど深く考えずに続けていることは見直しをする時間を持つとい