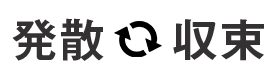Book:「採用基準」伊賀泰代 リーダー論/思考力についてあれこれ
今回はコース以外のところから創作活動にも参考になる気づきを書きたいと思います。
この本は、決断の効用って?、リーダーシップって?、グローバル人材とリーダーの違いって?、問題発見解決型の能力の源泉って?というようなキーワードに関心がある人にはとてもおすすめ。
いわゆるビジネスの分野での話のようですが、その他の分野であろうと異文化間でプロジェクトをする、もしくは考えを深めてアイデアを生み出していくことを仕事とする人、決断した後に起きることが怖いと考えて決断できない人、には役立つ内容だと思います。
日本で年末に購入して、そのまま後輩に譲るつもりだったのですが、20ページ以上付箋が張り付いたため、この本はキープすることにしてもう一冊新品をあげたという本です。
Amazonの紹介だとこんな感じ。
●概要
マッキンゼーの採用マネジャーを12年務めた著者が語るマッキンゼーと言えば、ずば抜けて優秀な学生の就職先として思い浮かぶだろう。
そこでは学歴のみならず、地頭のよさが問われると思われがちで、応募する学生は論理的思考やフェルミ推定など学んで試験に挑もうとする。
しかしマッキンゼーの人事採用マネジャーを10年以上務めた著者は、このような見方に対して勘違いだという。
実はマッキンゼーが求める人材は、いまの日本が必要としている人材とまったく同じなのだ。
だからこそ、マッキンゼーは「最強」と言われる人材の宝庫の源泉であり、多くのOBが社会で活躍しているのだ。
本書では、延べ数千人の学生と面接してきた著者が、本当に優秀な人材の条件を説くとともに、日本社会にいまこそ必要な人材像を明らかにする。
僕は、働いていたころからリーダーシップ論について関心を持って来ました。それは、会社で働き始めると、それまで自分が抱いていたリーダー像とは異なるタイプの方々がいて、それぞれ違う個性で部下や同僚を率いていたからです。それまで、リーダーといえば、声が大きくて背筋がピシっと伸びていて決断力があってなど、体育会系な印象が強かったです。
でも、たとえば体育会系ではなく声もぼそぼそと小さく話される方でも、優れた専門性やコミュニケーションの頻度と質の高さ、独創性とその説明能力などの高さで人を魅了して巧みに動かせる人がいることを知りました。
自分も、どう考えても、怒鳴ってビビらせて軍隊のように人を管理するリーダー像にはなれないと思っていたので、それ以外にも多様なリーダーシップの姿があるのを知って、自分なりのものを作り上げていこうと実践しようと努力したものです。
その後、日本を離れて暮らすようになり、異文化同士でのリーダー像もまた違うのを日々実感しています。そんなこともあり、この本の中に出てくるリーダー像や「本当に頭のいい人」についての言及はいくつか気づきがありました。
そして、さすが元マッキンゼーのコンサルと人事をされていただけあって、とてもロジカルにわかりやすく整理されています。目次をみただけで、何が書いてあるのかの検討がすぐつくし、読後は思い出すことも容易。さすがです。
特に気づきが得られたのは次のトピック。
- 誤解される採用基準
- 能力の高い人より、これから伸びる人
- 「マッキンゼー入社」を目標にしている人は採用されない
今や、マッキンゼーやボストン・コンサルティングなどの有名コンサルティング会社に入るための対策講座がMBAや民間にあるそうです。でも、著者はそういう人はほとんど合格しないと言います。
なぜなら、彼女たちが見ていたのは次の要素。
思考力=思考スキル+思考意欲+思考体力
ロジカルシンキングとか、MECE(漏れ無く重複なく事象を整理すること)などの能力は、あとから学習可能。でも、思考するのが好きな好奇心というのは、性格や習慣的なことだからなかなか育たない。思考体力は、どれだけ考えても疲れないタフさ。
僕がこの章を読んでいた時にちょうど、大手の外資系ファームに転職が決まった女性がいました。彼女は日本の財政や景気をリサーチする専門家でしたが、ビジネス分野の経験はなかったそうです。とあるきっかけで、ファームの人と知り合い、その人の薦めもあってケース面接といわれる「○○町の交差点にあるスタバの売上あげるプランを提案してみて」とか「この財務諸表を読んで企業分析して話してみて」のような即興の応用思考力テストを受けた。
財務指標に関する知識は乏しかったため、途中何度も止まって素直にわからないので説明してほしいと専門性のなさを露呈してしまったようです。しかし、思考すること自体は楽しく面接をしたコンサルタントとの思考のキャッチボールがどんどん進み、興奮して夜も寝られないほどだったそうです。結果、採用という結果を得ています。
そもそも、彼女はほんの少し前までコンサルの業界で働こうとも思っていなかったし、統計の専門家ではあってもビジネスの経験はありませんでした。でも、思考意欲+思考体力が非常に高く、そこにスキルが入れば優れたコンサルタントとして活躍できる見込みがあると判断されたのでしょう。
逆に、対策講座でAという問が来たらBという答えのような知識を蓄積して取り出す能力に長けている人は、合格しづらいそうです。
あと、この本には、経営者がほんとなら見せたくない弱みを聞くのがコンサルタントの仕事であるから、威張っていたり、見下すような態度の人は向かないという記述もありました。彼女は、その点も一緒に話をしていて人の話を引き出すのが上手でした。
- すべての人に求められるリーダーシップ
面白い事例が書かれていました。
簡単にいえば、町内会でお弁当が余った時に、「余った弁当を分けませんか」と発言できるようなことが全員型リーダーシップだと言います。日本の組織は役職に権限がつくことがほとんどで、権限がない人が発言をはばかられる空気ができやすい。この例でも、町内会長などの役員が何も言わないから、そのまま余ったまま放置されるか捨てられるのをみんなは不満に思いながらも見ているだけ。
しかし、この事例が例えば震災の避難所などでより適切に分配がなされなければならないときは、みなが率先して声をあげなければ、せっかくの食料も無駄になるし混乱が起きます。
自分の記憶を振り返っても、日本では学校生活の中でも、学級委員などのリーダーになると雑用が増えて他の人の分を世話するという印象を持ったものです。学級委員が次々と雑務を他の生徒に分配して、自らは組織運営や仕組みづくりをしたなんていう事例をぼくはほとんど聞いたことがありません。
でも、伊賀さんがいうマッキンゼーの全員型リーダーは、誰かがみんなの分のことを世話したり意思決定を代行したり、自分勝手にやることを主張するのではありません。効率よくプロジェクトを進めるための議論や役割の分配を進めることができ、その後の進捗を各自が責任を持って推し進められる組織です。
役職じゃないからとか、責任者ではなくても、組織全体の最適を考えて「その残ったお弁当、分配しませんか」と声をあげられるような人、そういう発言を躊躇しないことは、外国で暮らしていると特に大切な気がします。みんなかなり活発に発言しますし、会議しているのに発言しないとそれはそれだけのつまらない人だと思われます。
大学院での議論はかなり高度で、はやいので語学力と知識の双方が試されますが、僕もみんなにとって意味のある質問や発言を最低1つは絶対したいと思ってやってます。
- リーダーシップで人生をコントロールする
もう一つ面白かったのは、「ポジションをとれ」という言葉。多少拙速でも自分の意見・立場を表明することが、マッキンゼーでは習慣化されている。もちろん、ポジションをとることで批判や反対意見も出てきて困難に直面することもある。でも、そうすることではじめて改善や進歩が生まれる。
なんだこのくだりを読んでいて、会社を辞めてイギリスに来て今の学校に入ったことで、ああでもないこうでもないと頭のなかだけで考え悩んでいたことが遠い昔のように思えるほど、すべてが新しく動き始めたことを改めて実感しました。
ものごとは決断して、自分がその環境に飛び込んではじめて、うまくいきそうだとか、だめそうだとかわかってくる。その都度、修正の意思決定をしていけばいい方向にいくことが多いんじゃないでしょうか。もちろんギャンブルとリスクをとることは違うので、その事前準備を欠かすとポジションをとっても失敗する可能性が高いでしょうけれど。
そんなこともあって、自分も今のドキュメンタリー写真と社会・マーケットリサーチの手法を上手く活用して生活者や社会文化・問題に対する洞察をより深めることと、美的や内容に感動できるような物語としての両立に取り組みたいと、クラスやチュートリアルでも明言しています。言ってしまえば、どうやって、とかどう実際にやってるのとか、突っ込みが来るわけで、それがプロジェクトをすすめる推進力にもなります。まあ有言実行っていう言葉は昔からありましたね。
3つほど心に残ったトピックを紹介しましたが、本書はアート・スクールにいる今でも活用可能な要素を多分に含んでいる汎用性の高い良書です。
関連記事
-

-
西原理恵子の「あなたがいたから」
今回は、コースワークから離れて、漫画家の西原理恵子さんのことを書いてみます。西原さんからは仕事や家族
-

-
スポーツにおける観察と洞察力から学ぶ
欧州やインドにいたときは、サッカーばかり見ていたが、日本ではやっぱり野球を見る機会が増える。
-

-
Margaret Howell interview @FT / マーガレット・ハウエル インタビュー
The woman behind the international brand talks a
-
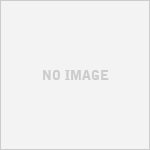
-
ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図〈2025〉
<Amazon.co.jpより転載> *下流民か、自由民か。地球規模で人生は二極分化
-

-
よき生産者になるためには、よき消費者であれ
20代のころに読んだ本に書いてあった言葉である。 確か、読書家で有名な立花隆さんの本に書かれて