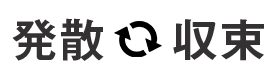スポーツにおける観察と洞察力から学ぶ
公開日:
:
本 / book

欧州やインドにいたときは、サッカーばかり見ていたが、日本ではやっぱり野球を見る機会が増える。
2009年ぶりに久しぶりに、高校野球、プロ野球を堪能した。サッカーのような流れの中のスポーツもいいけれど、一騎打ち連続のような野球には静と動の緊張感、考察する間があっていい。
シーズンも終わったが、それからは本を読む。漫画では理論的にとにかくセリフが多い「おおきく振りかぶって」、お金のことから選手を見る「グラゼニ」を読む。同じあだち充の「MIX」はそういう観点から見ると、ラブスポものであることを実感する。
書籍では、野村克也「無形の力 私の履歴書・野村克也」、岡田彰布「プロ野球構造改革論」を読んだ。これまでも数年前には、落合博満や野村克也の本は何冊か読んだ。最近だとザックジャパンの通訳矢野さんの「通訳日記」、NHK「プロフェッショナル ラグビー日本代表コーチのエディー・ジョーンズ」と面白い気づきだらけ。
ぼくが優秀なスポーツの監督やマネジャーが書いた本が面白いと思う理由は、いわゆるPDCAサイクル(Plan, Do, Check, Action)のサイクルをものすごいスピードで回し続けることで、気づきの蓄積が多いということ。
野村克也さんは、「観察と洞察のスポーツ」であると野球のことを言っている。故・島野育夫さん「よく見る。じっくり観察する。何でか考える。備える。的確な手を打つ」。
伊原春樹という元西部の走塁コーチ、監督、阪神コーチを歴任した方の観察と洞察、指示も学ぶところが多い。
1987年日本シリーズの2:08からを見ると、伊原さんが何を事前に知っていて、それをどう解釈、洞察し、選手に指示を出したかがよくわかる。
岡田さんの著書によれば、伊原さんはまだ巨人の優勝が決まる前からテレビで中継を見ながら、センターのクロマティが外野フライを取った後にゆるい球で返球し、かつ中継に入る名手川相は、一塁ランナーの進塁を主にチェックしているので、三塁ランナーは進塁しないと思い見るのがほんの数秒遅れるということを観察していた。
そのため、二塁にランナーがいてセンターに打球が行った時は、本塁を陥れるチャンスであると指示した。何度も使えない方法ではあろうが、日本シリーズのような短期決戦では決定的に役に立った。一度やったらバレるが、点がほしい一回分にはなる、そんなどこでこの一回を使うかというのも大事な意思決定。
僕は、本業のリサーチやアイデアを一緒につくっていく時に、洞察とかインサイトとかよく言葉が出てくるけど、学ぶべきフィールドはビジネスやサイエンスだけではなく、スポーツなど他の業界にも多いと思う。長く成功している人には、観察と洞察のサイクルをうまく回して改善と成長を続けている。
次は、阪神タイガース暗黒時代再び (宝島社新書)を読む理由。弱者を強くする専門家だった野村克也さんが、なぜ阪神では3年連続最下位だったのか。ヤクルトでは大地に水が染み入るように理論が浸透したにもかかわらず、「馬耳東風」であったということは聞いたが、もう少し深く知りたい。ちなみに、ぼくは小学1年生のときから阪神ファンで、最近はより面白い野球をしている球団に贔屓を変えようと思ったけれど、今更変えられないものですね。
関連記事
-

-
よき生産者になるためには、よき消費者であれ
20代のころに読んだ本に書いてあった言葉である。 確か、読書家で有名な立花隆さんの本に書かれて
-

-
路上は超芸術の博物館?!赤瀬川原平他「路上觀察學入門」
*** 内容(「BOOK」データベースより) マンホール、エントツ、看板、ハリガミ、建物
-

-
「アートのお仕事図鑑」美術手帖。アートやデザインの思考法は、広く求められている。
先日、TBSラジオ「ジェーン・スーの相談は踊る」を聞いていたら、リスナーからの相談メールで「
-
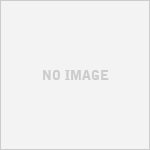
-
ワーク・シフト ― 孤独と貧困から自由になる働き方の未来図〈2025〉
<Amazon.co.jpより転載> *下流民か、自由民か。地球規模で人生は二極分化
-

-
「知る」「信じる」「感じる」とは。加藤周一さんの議論を振り返って。
日本に帰国する前後、科学の世界では世紀の大発見というSTAP細胞に関するニュースが出た。その後、プ
- PREV
- 発散と収束を日常で併せ持つ
- NEXT
- 見ることに関する考察