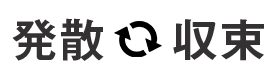江戸東京博物館で東京を300年ほど前から振り返る
公開日:
:
日常写真 / snap, ゆく未知/考えごと

一年で三度も訪れたという友人の奨めで両国にある江戸東京博物館に行った。さして歴史に関心のなかった人に一年に三度も有料であるにもかかわらず脚を運ばせるとは、無視できない存在である。
江戸東京博物館は両国にある、非常に巨大で不思議なコンクリートの建物で箱物感満載ではあるが、中は非常に見応えのある展示で魅せられる。1993年オープンとあるが、これまで全くノーマークであった。
江戸東京博物館にいくと人の暮らしは200年前後でこの位は変わるのかと気付かされる。どうやって時間を刻み、働き、給料をもらって子供を育てたかも。
自分は、20〜21世紀の時代をリアルに見て生きているが、過去からの知恵や風習を部分的にしか受け取っていないと最近思うようになった。
特に、東京に暮らすようになってそもそも東京がどのような経緯で成立したか、東京イコール江戸と思っていたけれど、実際江戸エリアはもっと狭くて、やはり今でもそのエリアは特別な雰囲気があること。住むという実感と、このような博物館の情報を合わせていくと、生活の中で新しい気づきがある。
人類の歴史や叡智は、大切なものはテキストになって教育され引き継がれるが、グローバルかつネットで高速に大量の情報が行き来すると、外へ向かっての好奇心も強くなり、もっとも身近な自分の住む地域の過去について疎くなりがち。それは地元だったり、今の住まいだったり、もしかしたら日本のどこかだったり。
僕自身は、品川に暮らし、少し前から道路の所々に橋の跡を見つけ、そこにかつて品川用水が通っていたことを知って驚いた。今日江戸東京博物館で、玉川上水の建造とそこから干ばつに苦しむ品川へ用水として江戸時代にひかれてきたことをジオラマで見た。生命の水を通し、やがて明治、大正、昭和ときて、生活用水としてその地位は下がり、先のオリンピックの際にとうとう暗渠として見えなくなってしまった。普通に暮らしていると、オフィスやマンションが立ち並ぶこのあたりがかつては農業用水を必要とする農地であったことを知ることはできない。しかし、かつて多摩の山から美しい水が、江戸時代にして一級の技術で東京湾まで引かれそれを使って人々が暮らしていたことを想像すると、気持ちが豊かになる。
あと、溜池山王に大きな池があったことや大名屋敷が流行り今でも一等地であることなど、おそらくそれ以前から続く土地の気質のよさを改めて知ることになる。
人は行きても80年前後、せっかくだからもっと土地や風土の記憶を広く聞き知って、引き継ぎながら暮らしたいと思う。
写真の手帳は、江戸の小売店が宣伝がてら店名や短いコピーを印刷して配ったもの。フォントがかっこいい。今なら、電話とURLは必須だけど何にもなくて潔い。
関連記事
-

-
武蔵野の秋風景@東京外大 / Autumn colour in Musashino area, Tokyo
武蔵野の秋風景@東京外大。美しい。 かつて戦後から東京オリンピックくらいまで、この地は関東村と
-

-
よき生産者になるためには、よき消費者であれ
20代のころに読んだ本に書いてあった言葉である。 確か、読書家で有名な立花隆さんの本に書かれて
-

-
星薬科大学裏門付近の桜
名所の桜も美しいけど、意外と近くにも立派なのがある。作家星新一の父親が創立した薬科大が隣にある。
-

-
My best writing tool /ベストの筆記具
最近は、パソコンで文章を書く時間を少し減らしています。 その代わりに、紙と万年筆
- PREV
- 見ることに関する考察
- NEXT
- 「猫楠」水木しげる