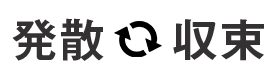光で描くことと光線漏れ

光線漏れ:外桜田門
セバスチャン・サルガドの「地球へのラブレター」とドキュメンタリー映画を見に行った。そこでは、フォトグラファーという職業の定義からしようと、はじまる。Photo(光) + Grapepher(描く)で光で描く者としている。
デジタルカメラによって、受光センサーに光が漏れることはあまりメジャーな故障ではなくなったと思うが、昔のカメラは単純にして言えば箱に穴があいているのと等しいものだったりするので、光が少しでも漏れ入れば写真に影響する。ピンホールカメラは、ほんとに箱に針で穴を開けただけの原始的なカメラでレンズもないが、ちゃんと写る。
そんな光を制御しながら写すということを実感したのが、Hasselbladのテストを兼ねて強い直射日光のある日に撮ったものがこれらの写真。
見事にフィルムマガジンという、フィルムを入れている部分に光漏れしている。これは、とてもメジャーなエラーで、部品が経年劣化すると起きるとのこと。光を防いでいるモルトというスポンジがへたって隙間が生じるのである。単純な話だ。

光線漏れ:虎ノ門外堀跡
一枚一枚かなり考えてそこそこ時間をかけて撮影が必要なHasselbladは、一枚に対する思い入れが強くなるので、このようなエラーは軽いショックがある。さっそく購入店に連絡すると、修理が必要とのこと。約2週間の空白が生まれる。一旦、カメラを持ち替えて観察をはじめたことをレビューせよという期間かもしれない。
写真は、構図とか以前に、物理的に失敗する可能性があるということを今更ながらに痛感したテスト撮影。本格的にプロジェクトで使う前にわかってよかったものだ。
さて、この二枚目の写真は、虎ノ門にある虎ノ御門の石垣跡。僕は品川区に住んでいるが、自宅の隣に旧中原街道という道があって辿って行くと桜田通でその先に虎ノ門があったのである。なんと一本道だったのだ。複雑な東京の町と道と思い込んでいたが、どうやらそれは地下鉄や鉄道のルートがそうなだけで実は道自体はシンプルなのかもしれない。都市と自分の関係性も、一旦乗り物から降りて、身体感覚を伴う形で歩いたり自転車に乗ってみると、ぐっと身近になる。遠くへ旅に行くのもいいけど、近くを深く知るというのもある種の旅である。そういう旅は、やろうと思ったら毎週できるかもしれない。そして、旅の醍醐味である非日常もそこにはあるかもしれない。
関連記事
-

-
Slow pace start of my course
新学期もはじまったかと思ったのですが、9月中旬までは施設やスタッフ紹介、器具の使い方など緩めのスケジ
-

-
ロンドン芸術大学ドキュメンタリー写真修士コースの中身
では、実技に重きをおきながらもリサーチも重視する方針に惹かれて選んだLondon College o
-
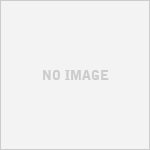
-
リサーチやテキストの重要性。写真家・米田知子さんインタビュー「感光される時間の層」を読んで
感光される時間の層 (English version: THE MULTIPLE LIVES OF
-

-
撮っておくべき写真カットの種類@LIFE誌方式/LIFE FORMULA FOR VISUAL VARIETY
フォトジャーナリズム”プロフェッショナルたちのアプローチ”というで雑誌ライフが求めた8つの写
-
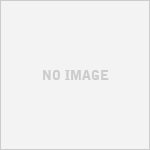
-
留学中の勉強相談 チュートリアル
今日は2回目のチュートリアルでした。 イギリスの教育システムでは、学生に対して指導教員が3~5名のチ
- PREV
- 桜咲く前の気配
- NEXT
- 戸越地蔵尊。旧中原街道沿い