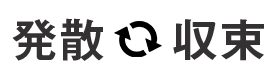路上は超芸術の博物館?!赤瀬川原平他「路上觀察學入門」
公開日:
:
リサーチの方法 / research method, 本 / book
***
内容(「BOOK」データベースより)
マンホール、エントツ、看板、ハリガミ、建物のカケラ…。路上から観察できるすべてのものを対象とした〈路上観察学〉。その旗印の下に都市のフィールド・ワーカーたちが集まって、隠された街の表情を発見する喜びとその方法をご披露する。街歩きが好きな人には、欠かせない、路上観察マニュアル。
***
古い建物や街道を眺めながら歩くのが好きな僕には最高に面白い本だった。NHKのブラタモリは、この系譜なんだろうなと思った。
フィールド・ワークというと、まじめにテーマを持って役に立つ分析をするものという印象を持つが、赤瀬川さんたちのフィールド・ワークは興味赴くままで半ば遊びである。ひたすらマンホールをスケッチしたものや、消えゆく赤坂の古い町にあった煙突に命がけで登っててっぺんからいまでいうセルフィーを撮ったものや、女子高生の制服スケッチ、破壊された建物のかけら集め、街角にいる動物たちの生態觀察記録などなど。とても趣味的なのに、時代がたった今、どれも貴重な町の記録である。
トマソンという概念自体がおもしろい。「赤瀬川原平らの発見による芸術上の概念。不動産に付属し、まるで展示するかのように美しく保存されている無用の長物。存在がまるで芸術のようでありながら、その役にたたなさ・非実用において芸術よりももっと芸術らしい物を「超芸術」と呼び、その中でも不動産に属するものをトマソンと呼ぶ」(Wikipediaより)
そういえば、読んでいて共感を覚えたのは、僕はどうやら知人に言わせると道路を蛇行するようにあっちこっちよりながらぐにゃぐにゃと歩く癖があるようだが、この本よればそれが一番觀察に適してる。そしてそれは、著者のひとりが近所の放し飼いの犬の後をつけて歩いて気づいている。そうすると、見逃しが少ないのだという。
土地に隠れている面白いものを探すには、純粋な好奇心によるおもしろい!が必要なのだ。著者のひとりである歯医者さんが、廃屋の瓦礫を集める趣味は決して本業の歯医者業に影響を及ぼすものであってはならない、と言いながらやっているのが納得だった。あくまで、趣味的であるからこそ、他人の目を気にせずつきねけた面白さが見えてくるものだろう。ウケ狙いで探しに行っても、なかなかみえてこないしそういう情報は雑誌なんかにあったりするのだ。
あと、文中でも言及されている、他人にやってもらったり大人数のプロジェクトになるととたんに面白みがなくなる、という指摘も興味深かった。昨今、クリエイティブなリサーチは、創りだす人が自分でもやるものという考え方がデザイン思考を始めに言われてきているので、ここでもやはり自分ごと、楽しんでフィールドに潜り込んでいくことが大事なんだよなと思わされた。
イギリスにいた時に読んだ「Phychogeography」なる、土地と人の関係を記した本も同様に町に隠されたおもしろきものに着眼するという点では同様である。古い港町には、そんな超芸術的な名残がたくさんあって発見が楽しかったものだ。
普段、目的地まで一目散に歩く道、自転車や車で高速で移動する町中、それぞれの箇所で少し立ち止まって眺めてみるとほんとは町は面白いものに溢れている。気忙しすぎて、ただ見ていないだけだったりするのである。
ちなみに、この本は伊豆フォトミュージアムのギャラリーライブラリーで見つけて買った。さすがの選書センス。
関連記事
-

-
「東京100年散歩 明治と今の定点写真」鷹野晃を読んで、品川の海側のことを思い出す
この写真集は、100年前後の明治時代の東京と現代の変化した町を対比で見せている。しかし、過度
-

-
西原理恵子の「あなたがいたから」
今回は、コースワークから離れて、漫画家の西原理恵子さんのことを書いてみます。西原さんからは仕事や家族
-
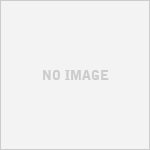
-
時間のみなもと ミヒャエル・エンデ「モモ」から
先日、ミヒャエル・エンデの「モモ」を友達何人かと読んで意見交換をした。 この話を、中学生のときに映
-

-
My first photo book KOOPI CEYLON 写真集ができました
大学院の卒業制作として、一冊の本を制作した。最終版まで3回の作り直しを経てついに完成。一刷目
-

-
アートリサーチにどれだけ時間を費やすのか/How long do you spend for your research of art?
今日は一日自宅で編集することにしていたけれど、窓の外に広がる一面の青空を見ていたら無性に外出がしたく
- PREV
- 高輪消防署二本榎出張所
- NEXT
- 中原街道のオアシス洗足池