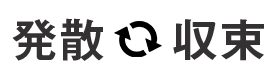「猫楠」水木しげる
公開日:
:
最終更新日:2015/12/10
本 / book
水木しげるさんが亡くなったというニュースを聞いたとき、そういえば「ゲゲゲの鬼太郎」、「のんのんばあとオレ」、「玉砕せよ」しか読んだことがないことに気づいた。
友達の紹介によれば、他の作品も全部すばらしいということで、その中でも特に気になった「猫楠」から読んでみることにした。
同じように、南方熊楠についても気になっていた。少年時代に「てんぎゃん」という熊楠の少年時代を漫画を読んだが、天才にして奇人で在野の研究者とは一体何者だったのか生涯を通しては知らない。
この作品は、最初の数ページから今手に取るべき本であった事に気がついた。
霊体の存在について猫楠と会話するシーンがある。(41ページ)

Physarum polycephalum. SCIENCE SOURCE
猫楠「しかし幽霊ってのは”幻覚”の一種じゃないのかナ」
熊楠「バカ。幽霊とよばれる現象は、幻覚や異常心理から作られるものではない純粋な空間現象だ」
「つまり実在の一形態でありそれを我々が知覚できるかできないかは全く”能力”しだいだ。まァ粘菌に例をとるとこいつは生と死を一つにもっているようなものだ」
「生命がもっとも活動しているときは見た目にはたんみたいなもので死物にみえる。後日繁殖の奉仕を守る粘菌は実は死物だが人は死物をみて粘菌が生えたという。活者同然とみるそれと同じで死んだらなにもないと考えるのはおかしい」
「案外死んで無くなってしまったというときに意想外の誕生があって我々が無上の価値だと思った”生”は実は”地獄”だったということもあるわけじゃョ」
人間は、目からの情報にかなり依存した生活をしている。外に出れば、歩きながらスマホを見るようになった最近はもっとそういう傾向が加速している。そうすると、隠れた次元とか世界はそのスマホの中にある考え方もあるだろうが、四次元目の空間が別にあるようにしてならない。
それは、五感をフルに稼働させて、熊楠(水木しげる)がいうような脳力を高める必要があるのだろう。この漫画の名脇役として猫が出てくるのも興味深い。猫は、目以外に音とにおいに敏感である。何かを知覚するのに五感をフル稼働して備える。闇の中での目がつよいのにはうらやましいところだが、逆に光にはあまり強くはない。
観察すること、洞察すること、分析的であり、ときに統合的に価値を生むことに注力した一年だった。この姿勢自体は、とてもよい傾向を生むようだ。
対象外という発想をあまりしなくなるし、一見違う分野のことを引き寄せてつなげる感覚が磨かれてくる。そして、この本と出会って観察すること洞察することの中に、目に見えにくいもしくは見えないことに気づくといことに関心が高まる。それを再構築して描き出せたらすてきだろうなと。出会うタイミングで気づく内容は変わってくる。だから、出会った時が読み時なのだろう。
水木しげるさんもお亡くなりになられて残念な気がするが、本書で言われている転生の過程へ進まれたのだろうなと思う。
追記
中沢新一さんとの対談もおもしろい。これは1991年の出版でそれから曼荼羅とか次元の話とか時代が追いついてきている気がする。
「現代の科学でユニークな可能性があるものは、みんな分裂的ですよね。ステファン・ホーキングの宇宙論もそうだし、生命論も脳の科学もみんなそうですよ。なぜそんなことをやるかと言ったら、コンピュータ自体が分裂しそうなんですよね。こういう現代だからこそ、それを全体的におさえつける思考体系ってのがない。ヨーロッパがつくってきた思想って、みんな分裂病の状態を押さえる体系なんです。そこで熊楠さんが考えていたような曼荼羅とか、妖怪や幽霊の世界、まあ、四次元の世界をベースにした思想というものでしか、今、人類に現れているものを捉えられなくなってしまったということじゃないですか」(中沢新一, 415ページ)
関連記事
-

-
よき生産者になるためには、よき消費者であれ
20代のころに読んだ本に書いてあった言葉である。 確か、読書家で有名な立花隆さんの本に書かれて
-

-
スポーツにおける観察と洞察力から学ぶ
欧州やインドにいたときは、サッカーばかり見ていたが、日本ではやっぱり野球を見る機会が増える。
-

-
「豊かさの栄養学 」丸元淑生を読んで、食生活について考えた
毎日繰り返していることなのに、それほど深く考えずに続けていることは見直しをする時間を持つとい
-

-
表現のこと 「考える人 村上春樹ロングインタビュー」より
大学の授業では、さまざまな課題がではじめました。 Photoshop、白黒プリント、カラープリント、
-

-
Book:「採用基準」伊賀泰代 リーダー論/思考力についてあれこれ
今回はコース以外のところから創作活動にも参考になる気づきを書きたいと思います。 この本は、決断の効