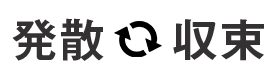ポートレイト撮影 相手のことを好きであればあるほどいい写真が撮れる?
公開日:
:
写真学び / Photography study Creation
なんて思っている。
写真というメディアに本格的に向き合い始めて2年がたった。やっぱり突然会った人より、その人のことをよく知っていて、どういうときにどんな表情するのかを知っているのは大切。もちろん仕事で撮影するときには、相手のことを十分しらないで短時間で撮らざるを得ないと思う。それでも、何らかの予備知識があるのは有効であろう。
その次に思うのは、そのすてきな表情はどんな光に照らされているときにもっとすてきかということだ。今のところ自分の好みは、朝や夕方の柔らかい光が窓から入っていて、それを正面あるいは斜め前から優しく受け止めている状態。写真には晴れより曇りの方がよく、光が強すぎたらレースのカーテンなどで更に拡散させると柔らかさがでる。リフレクターはあった方がいい。フラッシュを使っての撮影ももちろん必須だけど、できたら使わないで撮りたい。

魅力的な表情を魅力的な環境で撮った写真は、ずっと眺めていたいと思うほどすてき。これは写真がよいというより、その人らしさが存分にそこに写されているわけだから、その人自身がいい!のだと思う。
自然光ではないときでの好みは、町のいたるところにある街灯や看板などのスポットライト。これを上手く利用すると、闇の中で表情がクローズアップされて美しい。それに気がついてから、暗くなってからの街歩きも違った楽しみが出来た。ここは撮影に使ったらいいだろうな、と。

同じことは風景や建物にも言える。それらが見せる表情というか、取り巻く環境も時間とともに異なる。太陽が照らす位置は刻々と変化するし、まわりに人や車がいて違う印象をもたらすこともある。またレンガやタイルに設計者のこだわりや歴史が刻まれていることもある。
そういう意味では、家族のスナップなどはプロの写真家でも撮れない瞬間や表情を捉えていることが多いと思う。
総じていえるのは、やっぱり写真にもリサーチというか事前準備が大切だなということ。どれだけ撮る対象のことのことを知っているか好きになれるか。
以前、チベット仏教のラマを撮らせてもらったとき、ラマのことを数日ネットや書物で調べて臨んだ。ラマたるもの、深刻な表情たるものという思いこみがあった。撮った写真を後日送ったら、「私はいつも笑ってるのよ。笑った写真も撮ったじゃない。そちらがほしい」と仰られた。おそらく、身近で時間を過ごせば彼女のことのそういう姿がすてきだと気づいていたかもしれない。でも、そのときは1時間以上撮影に時間をもらったにもかかわらず、気がつけなかった。1時間はその人を知るにはあまりに短い。でも、得てしてそういうズレが相手のことを知る一歩なのだろう。
まだまだ発展途上の自分だけれど、そこは大切にしていきたいと思っている。
今回は、エッセイスタイルで書いてみました。
関連記事
-
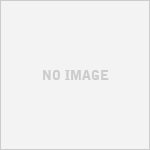
-
St Mary Rotherhithe(Charity school) / 聖メアリーロザハイス(無償塾)
‘Founded by Peter Hill and Robert Bell in 1613.
-

-
ナチュラルコーヒー@Kandyのメニュー写真を撮りました/Natural Coffee Menu
メニュー写真撮り。森で採れたコーヒーたちが加工、焙煎をへて、商品としてお
-

-
Summer term has started!/夏学期がはじまりました!
4月15日から夏学期が始まりました。約一ヶ月近く春休みがありましたが、実際は実技と理論のエッセ
-

-
Assignment_5 Environmental Portrait 03: Tony, Head Doorman in The Savoy
SAVOY HOTEL is one of most luxury hotel in Lon
-

-
Rethink Project 01. Topic / プロジェクト「再考」のテーマ設定(日本語あり)
Until 21st June, I will devote my time to Rethin