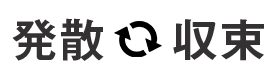写真学科卒業後の経済的自立について

最近、ロンドン芸術大学写真コースの経済自立の支援教育に関して進学希望者から相談を受けました。また、インドで写真を学ぶことに対して疑問を持ち始めたという学生の話を聞いて、写真を学んでからどのような仕事の方向性があるのかを考えさせられましたので、そのときのことを記しておきたいと思います。
いわゆる芸術大学の中で音楽やパフォーマンスを除くと、卒業後に生計を本業で立てるのが難しいのは、美術(ファインアート)や写真ではないかと思います。
このことは、ロンドン芸大にいたときトピックとしてよく話されていましたし、インドの国立デザイン大学院でも同様の傾向があるようです。また、僕のまわりの芸術大学出身の人々を見ていても、美術や写真で生計が成り立つ率は結構低いという実感があります。
ロンドン芸大の経済的自立サポート
ロンドン芸大では、私が所属していた基礎コース、修士のドキュメンタリー写真コースと、コース単位の取り組みと、大学をあげて行う卒業に際して経済的自立へのイベントを1週間くらい行うものがありました。アーティストやデザイナーのレジュメの書き方や会計、法律から活躍する卒業生の事例など、知識だけではなく実際に人脈を気づくこともできます。ただ、これは最後のイベントですので、それ以前の準備となると個人とコースでの活動が大切になります。
コースでの取り組み
ロンドン芸大の学生たちがもっとも学びたいことの一つも、経済自立でした。そのため週一回成功している写真家やエディターを招きレクチャーを依頼していたのです。
概ね、私にはアーティスト活動をしながら、生活費を稼ぐために結婚式やイベントのカメラマンやビジネスポートレイトを撮影している人が多かったように思います。共通していると思ったのは、みんなそれなりに余裕がない中やっている感じでした。経済的な面を語るときに、好きなことをやっている清々しさと苦しさの間くらいの表情で語る人が多かったです。
映像制作会社を設立した卒業生
唯一、経済的に成功しているイギリス人の卒業生(女性)は、映像制作の会社経営をしている5年前の卒業生でした。
彼女は、5年前からドキュメンタリー写真コースにいながら動画を活用した作品づくりをしていました。ただ、まわりには白黒写真とか美術、純粋なフォトジャーナリズムを目指す学生がほとんどだったといいます。修了プロジェクトで制作した作品は、これは写真じゃないと先生に酷評されたといいます。
もうひとり、BBCなどのタイムラプス(24時間を短時間で見せる超高速映像)を制作している卒業生も、写真コースでは動画ばかりを扱っていました。課題以外で彼が写真のプロジェクトをやっているのを見たことがありません。
5年前はそうでもなかったかもしれませんが、最近の写真コースでは、マルチメディアを活用した動画や音を含めた作品は一般的になっていますし、彼女はその後動画に特化した映像制作をジャーナリズムと広告業界に広げ、割りと大きな会社に成長させました。市場ニーズに合わせた形で事業を展開し、自分の作りたい作品は自前でやります。
フォトグラファーの地位
写真家というかカメラマンも含め、写真が綺麗に撮れる人の相対的価値は年々下がっていることでしょう。10万円未満の一眼でもかなりきれいに写真が撮れるからです。
もちろん、雑誌や広告などに使われる写真はプロが制作したものです。しかし、もう少し低予算で依頼されたいた仕事は減っているはずです。たとえば、以前であればプロのカメラマンに依頼していた小中学校の修学旅行も、写真が趣味の先生がデジタル一眼レフを持ってきて撮影しているのをよく見ます。2013年にはシカゴ・サンタイムズの写真記者が全員解雇になり、取材記者が自分で撮影するようになったとの報道もありました。
インドの国立デザイン大学院の就職課も、写真デザイン科の学生がもっとも職を探すのが難しいと言います。
車や服、家具のデザインと比べ学んだスキルや経験をクライアントに示しづらいのだと考えられます。積み上げる知識が科学的なもの(再現性の高い方法論)ではなく属人的なアートの部分が強いとみられるからかもしれませんし、実際、写真学科の学生も自分はアーティストであると考える傾向があるからだと思います。
もちろん、プロや専攻している学生が撮る写真は、技術的や表現として質が高いです。しかし、それがそれなりのお金を支払える価値であると考える人は10年前に比べ減っているのではないでしょうか。
卒業生の一人は、我々の業界には、すごく資産を持っているか、配偶者が金融関係や医者など経済的に裕福な環境が実際にはかなり多い、とぶっちゃけてくれた人もいました。
一年間もそんなOB、OGたちの話を聞いているとなんとなく写真家やカメラマンという人たちのタイプやポジションが見えてきそうではったのですが、ひとつひとつの事例をインサイトに昇華するような議論はできませんでした。
アートとデザインの違い
卒業後一年近くたって、インドの学生たちやパートナーと話すに従い少しずつ考えがまとまってきたように思います。
それは、アート(ジャーナリズム)、デザイン、ビジネスの重み付けを各自がどのように意識して、自分のポジションや仕事を形成していくのかということです。
芸大に入るまで、私はデザインとアートの違いについてあまり考えたことはありませんでした。どちらも似たようなものであろうと。
しかし、この両者は異なります。アートは、問いやメッセージを作品を通じて発する表現の領域だとすると、デザインはアートやコミュニケーション、エンジニアリングなどあらゆる知や表現、メディアを使って問題解決の解を提示する仕事だといえます。そのため、デザインにはほとんどの場合、クライアントが存在するはずです。一方、アートは自分発であることが多い。
デザインには、問題発見能力、コミュニケーションやソリューション提案という能力が必要になるし、そこに自分の創造性をどう織り込んでいくかも問われます。インドのデザイン大学院(NID)にある写真コースは、写真デザイン科といいます。私はそのネーミングを結構気に入っています。その観点からいえば、写真学科もアート(問いやメッセージを発する表現)とデザイン(問題解決のための表現)の両方の視点が必要なのだと思います。
ただ、大学に写真を学びに来る学生の大半は、アーティストかジャーナリストマインドが強いという印象を持っています。
写真の分野であれば、クライアントから撮影の依頼を受ける仕事は、デザインの要素を多分に含む仕事だと思います。クライアントの要望に応じて、意図通り撮影して仕上げたり、クライアントも気づかなかった価値を表現して見せたり。そういえば、先日、クリエイターの大宮エリーさんが、自営業であれば何でもできる自由があるかといえば、そうでもなく料理にたとえればメインディッシュはクライアントの要望、自分の創造性は刺身のツマみたいなもの。だけど、それがとてもレベルが高いもので驚いてもらうといったようなことを言っていました。そういう、信頼関係ができてくると、きっと仕事の自由度はより広がっていくのでしょうね。
完全に、自分のやりたいようにやっていけるとしたら、それはそういう信頼関係を過去に築きあげたか、突き抜けた才能を持っている場合じゃないでしょうか。
写真学科に関しては、既存の写真というメディアに留まるだけではなく、共創の中でも写真を活かした活動ができるはずです。デザイン大学には大体イノベーションマネジメント系の学科やニューメディア系もあります。そこにはビジュアルイメージのデザイナーとして、写真のリサーチや撮影、展示に加えて、写真の新しい表現や活用方法があるはずです。
マーケットという視点
本業として活動を続けていくには、マーケット規模を考えることも大切だと思います。例えば、伝統的に写真学科では展示会、写真集、作品販売、雑誌掲載、というがありますが、市場規模は大きくありません。自分のまわりの一般的な友達に一年に写真集を何冊買うかやギャラリーにどれくらいの頻度で行くか聞いてみると実感できるはずです。
そういったギャラリーなどの発表の場には、オピニオンリーダーやキュレーターも訪れるでしょうから、大事な場であるのは確かです。同様に、コンテストに入賞することも重要でしょう。
ただ、より多様な人に見てもらいたいとか、違った収益モデルをつくって継続して創作する資金をしっかり稼ぎたいというなら、それらに加え新しい取り組みが必要なのだと思います。
そういう観点から考えると、フォトグラファーのギャラが下がっている!とか仕事がないと怒る気持ちはわかるのですが、市場や社会環境の変化ですから自らも対応していく必要があると私は考えます。
新しい挑戦をするときなのです。隣接するメディアや専門性を横断的に見ながらコラボや取り入れていくのも、続けていくには大切ですし面白いと思います。
自分の立ち位置
私自身のことを振り返ると、元々、マーケティングの分野でデータ分析やフィールド調査を仕事にしてきたこともありビジネスに強い関心をもっています。
ただ、合理主義やロジックが大切とされるビジネスでも、アートやデザインの要素はとても大切です。特に、ブランドへの共感や生活者の理解には、感覚的に腹に落ちるというアートの要素が多分にあります。また、バックグラウンドが異なる人々と共創するときにビジュアルやサウンドなどメディアの力は大きいです。そんなモチベーションで新たに芸大で写真を学ぶ私のポジションは、描き出すとこんな感じだと思います。

私にとって写真は、自分で撮ることも大切ですが、写真を活用して何を引き出すかも同じくらい大切だったりします。
たとえば、ビジネスにはほとんど関心がなくても、アートという観点に、デザインの発想が加わると、なぜ写真でその対象を表現する必要があったのか、という問いすら浮かんでくるかもしれません。その対象を描いたり、表現して伝えるのに、より向いているメディアやその組み合わせもあるはずです。
アートとビジネスの部分のみが別に語られることが多かった留学時代を振り返って、今なら、デザインという発想を混ぜながら両者をつなげていけるのではと考えたりしています。
もちろん、自分が追い求めるテーマは大切です。情熱が持てないことは続けられません。しかしそれだけでも、プロジェクトを持続させることは難しいはずです。そのため経済的自立ということを考える時に、一度この3つの重み付けが自分の中でどのようにあるのか認識して、取りうる道(戦略)を模索するのがよいのではないかと思います。
関連記事
-

-
KOOPI CEYLON e-book edition
かつてセイロンと呼ばれたスリランカにおけるコーヒーの復活に関する物語です。150年前に、世界
-

-
A Japanese teacher in a small village in Uganda
Teacher R. on Flickr.
-

-
撮っておくべき写真カットの種類@LIFE誌方式/LIFE FORMULA FOR VISUAL VARIETY
フォトジャーナリズム”プロフェッショナルたちのアプローチ”というで雑誌ライフが求めた8つの写
-

-
スリランカでの2ヶ月のフィールドワークと撮影開始
My new research has just begun. I’m visiting Sri
-

-
Assignment5 Environmental Portrait 02: Luis, The Calder Bookshop & Theatre owner, 42.
My life in London had begun in Waterloo in 201