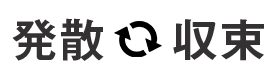Re-Think Project 2016

Hassel最初の一本から
ロンドン芸大のドキュメンタリー写真コースの修士課程のとき、Re-Thinkプロジェクトというのがあった。
今までの自分のやり方や考え方を捨てて新しい方法で一ヶ月ほどプロジェクトをしてみようという取り組みである。
僕はそのとき、デジタルの動画で取り組んだものだった。そのときのコースメートの多くは中判カメラに持ち替えて写真を撮っていた。僕は、アナログは正直なところ手間がかかるし、生来のデジタル好きが味方して、一行に関心をもつことができなかった。
2016年になって、僕の写真とのつきあい方は、デザインリサーチ、エスノグラフィのビジュアル情報となっている。より多くの写真をメモとして記録していき、インタビューの内容とともに意味合いを解釈していくのである。
それはリサーチやビジネスの文脈では、たいへん有益ではある。
しかし、一方で、写真そのものへの関心は低くなっていくばかりであった。デジタルでメモのように撮った写真は、仮に35mmのフルサイズの一眼レフで美しくとっても、たくさんある電子情報の一枚でしかなく、素通りしてその多くはHDDの中に埋没するばかり。
さて、2016年になったときに、今年は、実験的要素を持った創作をしていこうと誓った。同時に、見ること、写すことをもっと丁寧に身体の感覚を飛び済ませて行っていきたいとも思った。
そこで、具体的なアクションとして、撮る前にじっくり見る、対象をイメージするというプロセスを大切にするため、アナログの中判カメラを使って見ることにした。
近所や新宿の中古カメラ展をはしごしながら、気が付くとHasselbladを探し求めていた。アポロが月面へ持って行ったあのカメラである。一日のリサーチと二日間のフィールドワークを重ね(笑)、500C/Mの1983年モデルに出会うことができた。昔は、プロカメラマンのステータスと言われシステムを揃えたら車が買えると言われた銘機。
さっそく、翌日12枚分のフィルムを撮影してみた。フィルムの装着、ファインダーを覗き込む形状、ピント合わせ、ライトメーターでの測光、シャッター、巻き上げと、すでに全く異なる写真体験。そもそも被写体に向かう時間自体が長い。
いくつか撮った中から、家のヤンマールをのせておきたい。暗い部屋の中だったので、シャッターの速度が遅くてヤンマールは顔を動かしたので顔のピンとは少しずれている。
でも、なんだかこの一枚が妙によくてずっと眺めている。もう少し何かが変わりはじめているのかもしれない。
今考えている、東京での創作プロジェクトは、使う道具からして変えて進めていきたい。

関連記事
-

-
提出 Project three: ‘Forgotten’
Sony A900 with Tamron A09 28-74mm Mode: Ape
-

-
ポートレイト撮影 相手のことを好きであればあるほどいい写真が撮れる?
なんて思っている。 写真というメディアに本格的に向き合い始めて2年がたった。やっぱり突然会った人より
-

-
Arabica coffee cherry in a forest, Sri Lanka/森で育つアラビカコーヒーの実
The ripping process is different even in the sam
-

-
作品を見る時間を作家がコントロール Ayşe Erkmen: Intervalsより/The artist controls the audience’s viewing time
あなたは、丹念に作り上げた自分の作品が、展示場で1秒くらいで見終わられたらどう思うだろう。芸大で
-

-
アプリBrainPlotsは、いままでのブレストをどう進化させるか?
独立して働くには、アイデアのパス交換の相手をどうやって探すかは大切な課題です。 会社員
- PREV
- 見ること、見せることについて@東京藝術大学修了展
- NEXT
- 道具を持ち替えて目黒不動を撮る