ジュガードという思考法。悪しき習慣かイノベーションか、スタンフォード大Dスクールにも事例あり。
公開日:
:
リサーチ方法 / research method, 習慣 / custom
インドにはJugaad(ジュガード)という言葉があります。
この言葉の定義をどうするかという点については、インド人コンサルタントが教えるインドビジネスのルール (中経出版)によれば、「斬新な工夫による応急処置」とし、もともとは「1980年代にパンジャーブ州の村人達によって考案された自主制作の車に由来し(中略)、その土地の普通の人々が幾人か集まって造った車であるため、これといったデザインも、安全性への配慮も、車に関する規制への準拠もありませんでした」が起源です。そのような経緯から、突貫や突飛なアイデアでなんとか場を取りなすという消極的な意味と、限られた資源の中で工夫して物事を成し遂げるという付加価値を含んだ意味があります。
有名な事例だと、電気洗濯機でラッシーをかき混ぜる、電気の要らない水冷冷蔵庫、足漕ぎ洗濯機などはジュガードイノベーションの成功事例として語られています。
私が、実際の生活でこの言葉を実際に聞いたのは、インド人の友達がヘルメットの中にある発泡スチロールの緩衝材に氷を入れてクーラーボックスとして使っているのを見た時です。お互いに「ジュガード!」と言って笑ったのを思い出します。
Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growthによれば、ジュガードは次の6要素で構成されているといいます。
- Seek opportunity in adversity/逆境の中でチャンスを探す
- Do more with less/少ない投資で最大の効果をえる
- Think and act flexibly/柔軟に考え行動する
- Keep it simple/シンプルにする
- Include the margin/今主流ではないターゲット層も考慮
- Follow your heart/思いに従う
私は、特に二番目と三番目にインド人のジュガード哲学を感じることが多いです。
ジュガードマスターことジュガードゥ
正規ルートでできないことを裏ワザでやってのける人のことをジュガードゥというそうです(『インドビジネスのルール』)。
彼らにお願いすれば、入学試験、入社、電車の予約など様々な表側からのアプローチでは不可能なことを縁故や力を使ってやってのけるそうです。
私は、この言葉を生活の中で聞いたことはありませんが、きっとビジネスを起こすときには必要なのかもしれません。
インドではありませんが、スリランカでビジネスを円滑に進めるためにキーマンを動かすことで、動かないことがスムーズに動き始めるのを何度も目にして、ジュガードゥのような存在がいることに気がつきました。そう考えていけば、日本にもそういうのありますよね。
一晩で社員になって日本企業との会議に出席
そういえば、面白い経験をしたことがあります。
大学でアーティストを招いて講演会を行った際、パートナーは通訳兼司会、私は写真を記録として残していました。
講演が終わり、地元の新聞社の取材が入る際、最後にとあるグジャラートに本社を置く会社の紳士が礼儀正しくやってきたのです。何やらお願いがあるような素振り。聞いてみると、明日大事な会議があって日本語スタッフが足りていないから急ごしらえで臨時社員になって出席して助けてくれないかというものでした。聞くところでは、地元で語学学校や通訳者派遣を行っている会社の社長でした。
どこかで何とか適任者を探さないといけないと思ってやってきたのが、新聞で告知も出ていた国際アーティスト講演の会場だったのです。
まずそのリサーチ力はなかなかです。そして、仕事は明日午後とのこと。ほんとうに切羽詰まっているようです。
どうしても、会議における情報の秘匿性についても問題なさそうな初期段階の打ち合わせということでしたし、どうしてもお願いしたいとのことだったので私は受けることにしました。
翌日、車で迎えに来てくれたときには、既にその会社の名刺が印刷され用意されていました。なんでも時間がかかるインドで、このスピード感はすごい。
そして迎えた会議は、日本やインドで有名な大手製造業とのものでした。
自社の大一番に向けて、ぎりぎりなんとか形だけはまとめてしまうという粘り強さなのか、計画の甘さなのかわかりませんが、とにかく会議は問題なく終了したようでした。
会議での通訳が無事終わると、終了後に日本の会社とやりとりする際のビジネスマナーについて意見交換をしました。
こういう最後になんとかする、諦めてしまわないでとにかく動いてお願いしてみるという積極性は見習うべき点でもあるなと思ったりしました。こういうのも、ジュガード精神だなと感じたものです。
ジュガード精神をイノベーションに活かす
はじめのころは、予めしっかりスケジュールをたてて、工程表を作っておけば土壇場で準備が滞るなんてことはないのでは、と考えたものでした。
未だに、その部分はその通りだと思います。
その一方で限られた資源、能力、予算の中で、なんとか目的を叶えるという問題の本質から考える柔軟な発想は、学ぶところがあると最近では考えています。
最後に、さまざまなジュガードイノベーションの具体的事例を集めたサイト“Jugaad in Action”をご紹介いたします。Embrace Co-Founder and CEO Jane Chen(下記動画)さんの会社は、スタンフォード大学デザインスクール(通称D-school)から発足したインドに相応しい保育器を考えた末生まれた事例です。
通常、保育器は病院にあってプラスチックのケースでできており赤ちゃんの健康を維持するのに必需品です。しかし、インドでは病院に通えない人が多く乳児死亡率を押し上げていました。
そこでDスクールの異なる専門の学生が集まり、現地で徹底したフィールド調査をして体温を保温できれば機械である必要がないことと、インド人は医師の処方を守らず自分でさじ加減するから、その点を改善することが一番大事だということに気がついたメンバーが低予算で開発し普及させた商品です。(クリエイティブ・マインドセット 想像力・好奇心・勇気が目覚める驚異の思考法に詳しく出ています)
先に上げたジュガードイノベーションの6要素を引用しました。それらとEmbrace社のようにリサーチで得た本質的な気づきを、既存のものから自由になってどのように製品やサービスにしていくかという点でもジュガード精神は活きています。その点から考えても、イノベーションという文脈では、学ぶところの多い精神だと思います。
関連記事
-

-
人間ウォッチングで社会や個人のニーズを読み解く「サイレントニーズ」ヤン・チップチェイス著/Hidden in Plain Sight
Hidden in Plain Sight: How to Create Extraordi
-

-
インド首相モディ氏、Twitterフォロワー820万人への発信とグローバル社会への影響力。Googleアドワーズで比較。
インド最大の英字新聞The Times of India(8月27日)にモディ氏のTwitt
-

-
アート、デザイン、サイエンス、ビジネスが交わる実験場。Godrej India Culture Lab。
インドで様々なビジネスを展開しているゴドレジには、異分野、異文化との交流
-

-
インドの婚活・新聞広告編/How to find the right one on newspaper
インドでThe Times of Indiaという新聞を購読しています。英字新聞では最大規模で2
-

-
【祭】オーナムのお祝い/Happy Onam
オーナムは、インドの南西ケララ州のお祭り。インドの神話で阿修羅王が地下からケララに戻ってくる
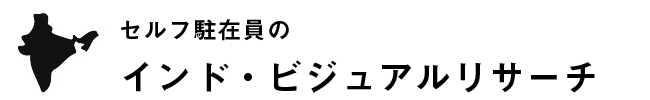







Comment
[…] ンか、スタンフォード大Dスクールにも事例あり。 https://pear.minibird.jp/pblog/?p=1104 […]
[…] ンか、スタンフォード大Dスクールにも事例あり。 https://pear.minibird.jp/pblog/?p=1104 […]