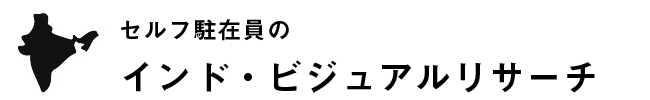人間ウォッチングで社会や個人のニーズを読み解く「サイレントニーズ」ヤン・チップチェイス著/Hidden in Plain Sight
公開日:
:
リサーチ方法 / research method

Hidden in Plain Sight: How to Create Extraordinary Products for Tomorrow’s Customersという観察法とそのまとめに関する本を読みました。邦訳も出版されており「サイレントニーズ」といいます。私が読んだのは原著の方です。
この本では、市場から生活者や顧客の特徴を分析して、アクション・プランにつながるアイデアへと昇華させていく各プロセスで必要な観察法やその解釈について実体験に基づいた内容が紹介されています。観察の素養を養うという意味では、消費財や耐久消費財のマーケティングだけではなく、従業員や学生の勤務や学習状況や満足度といった組織内の観察にも役立つと思います。
本書との出会い
この本は、知人の紹介で一度ハードカバーで購入したのですが、インドに向かうときかさばるので読まずに置いてきてしまいました。デザインリサーチで著名なチップチェイス氏が記した本なので、きっと色とりどりの写真やイラストに彩られた本を予想していたのですが、手に取ると一章から結論までのテキストのみで論文形式でした。正直この段階で、少しがっかりして机に積み上げてしまったのです。(その前に読んでいた”Creative Confidence”という本の作りがすばらしかった反動だと思います)
しかし、インドでの生活をはじめてから心の片隅で、この本の存在が気になっていました。国際的に活躍しているリサーチャーである著者は、インドで何をどう観察するだろうと思ったからです。そこで、Kindle版を改めて買って読むことにしました。同じ本を自分のために二冊買うのは無駄か、と思ったのですが、再購入の判断は正解でした。
「自分はプロの写真家ではないけれど、プロの観察者」
著者のヤン・チップチェイス氏は、モトローラやデザインコンサルfrogで豊富なリサーチ経験を積み、そこで実際に機能したリサーチの方法論を語っています。ウガンダ、インド、日本、韓国、中国、アメリカ、アラブなどの新興国から成熟国の市場まで、携帯電話や電子マネーを中心とした多様な事例が登場しています。最初の事例に、インドにおけるポルノ動画の流通に携帯電話と無線中心がおじさんたちを中心に広がっているという事例が出ていて、読者の好奇心をかき立てているところなどもさすがです。
著者は、「自分はプロの写真家ではないけれど、プロの観察者といえる」と述べており、観察の専門家です。
リサーチの教科書では、フィールドリサーチにおいては、気付きのメモが大切だとされています。その中でも、写真は気付きを記録する重要なツールです。テクノロジーの進化で、スマートフォンですらきれいな写真を残すことは可能です。しかし、撮影対象をどのように決め、いつどこでどのように観察し何を記録するのかについて、実際にはあやふやな点が多いのも事実です。特に、外国の未知のフィールドでは、わからないことだらけでしょう。
ありのままに見る、分析する、というのは文化人類学者がエスノグラフィーという方法で探求していることです。この方法は、マーケティング分野でも頻繁に活用されるようになっています。
しかし、どこに目をつけて観察し、観察対象から何を導き出せばいいのか体系建て説明されているものは少ないように思います。それこそ、リサーチャーやマーケターのセンスに任されている部分です。私もセンスの大切さも大いにあると思いますが、そのうちいくらかは、コツとして学べるものだとも考えています。
「サイレントニーズ」はそういったコツをいくつか提供してくれています。フィールド観察において有益だと思われるポイントを抜き出してみました。見出しだけを本文から引用し、後は私の感想です。
鮮度の高いうちにデータや情報を使う / “Data, like milk, is best consumed fresh”(p29)
できるだけすみやかに集めたデータを分析し解釈すること。その前に、観察した記録はできるだけその日中に(できれば観察後すぐ)、整理し不足分を記憶の中から呼び起こしメモに残す。写真にも、必要なキャプションを入れる。時間の経過とともに人の記憶は、消えていく。
これは、私が家電メーカーのリサーチャーとして働いていた頃(2003〜2011年)にも重視していたことでした。
グループインタビューやデプスインタビュー、あるいは顧客宅訪問でも、丸一日かかる観察の仕事です。夕方終えたら、すぐにでも飲みに行きたい気持ちになりますが、可能な限りその日の内に30〜60分一本勝負と銘打って、マーケター、商品企画者、デザイナーなど参加者全員から気付きをあげてもらう短いミーティングを行いました。
それを、エクセルに記録しておき、帰宅後、分野ごとに簡単に整理します。それをフラッシュレポートと呼んでいました。
そうすることで翌日には、参加者がそれらを見返しながら、次のアクションのヒントを考えだすことができます。今思えば、このプロセスは、観察という同じ経験を違った立場や専門性から持った後、ワークショップで気付きというアイデアを発散させ収束させる共創のひとつの段階だったとと言えます。
実際、毎日、商品や顧客のことを考えている優秀なマーケターや商品企画の多くは、観察を終えた段階でいくつかの戦略的な仮説を自分の中で数個かに収斂させています。そして、できるだけ速やかなアクションをおこそうとしているものです。一週間後に分厚いレポートが出てきたところで、もう記憶とリアルさの賞味期限は切れかけて価値は半減していると言ってよいでしょう。
発見の多いリサーチというのは、フォーマルとカジュアルな方法のバランスの上に成り立つ。
“Often what separates good design research from great design research is finding the right balance between formal and informal data collection, “ (p149)
先日、大手家電メーカーのインド支社で、テレビやデジタルカメラなどのマーケティングを統括されている方のお話を聞く機会がありました。その際に、インドで精度が不安定な定量調査をしている時間とコストがあるなら、日々たくさんの生データや現場に触れ考えを研ぎ澄ませている自分やメンバーがフィールド調査で得た気付きの方が有効であることが多い、とおっしゃっていました。もちろん、誤りもあるでしょうが、早く判断して動き出し間違いがわかった時点で修正していく身軽さがあれば、定性的なアプローチで得たインサイトの方が使い勝手がよく、活用度合いが高いことの方が多いでしょう。
問題は、それの結果をもって、リサーチに参加していない人を説得することだと思います。そのあたりのことは、ヤン・チップチェイス氏が日経ビジネスで日本企業は「データを重視し過ぎ」と述べています。
「クリエイティブのプロセスでは、直観が何よりも重要です。直観とは、人生経験に根差した、はっきり文章化できないにせよ「これは正しい」とピンとくる感覚のことです」
リサーチには、フォーマルなものとカジュアルな段階のものがありますが、フォーマルなものの流れは、下記の図のような流れになることが多いです。それはそれで大切ですが、この”課題の明確化”、”仮説”設定、”考察”の段階には、いずれもカジュアルなレベルでの経験で現場感を持っていることがリサーチ結果に大きな影響を及ぼします。
それがなければ、数字は集まりますが、それが何を意味するのかやそこから何を読み取ればいいのかわからないでしょう。
本書の中では、カジュアルなリサーチは一見遊んでいるようにすら見えてしまうので、クライアントから怒られそうなのですが、実は重要なのだと述べられています。
手っ取り早く異文化に溶け込む / “Rapid cultural calibration” (p126)
数時間から半日かけて、ローカルの床屋やレストラン、通勤電車などを利用して、地元の人々とのふれあいの中で、その国や地域の文化の実体験をする。結局、こういう方法が一番実感を伴った濃い経験になるのだと思います。
私も、インドに来てから現地の人々と同じ経験をしたときにはできるだけ記録を残すようにしています。こういった即効性のあるカジュアルリサーチで全てが明らかになるわけではありませんが、仮説の源泉になったり、データを読み解く時のヒントになります。
町とともに目覚める / “waking up with the city”(p127)
平日、日の出とともに目覚め、朝の町や人々を観察することで得られる気付きは貴重。規則正しく動き出す町の仕組みを見るには朝が最適であり、夜はあまり向かないと著者は述べています。
各年、朝ランニングやエクササイズをしている人たちの層を比較したり、通勤の様子を観察し、その土地の人々の生活背景を押させておくことは基礎的な部分だと思います。また、町がまだ準備段階の時間帯に、どんな人が何をしているかは地域性や国民性などを押して測るときに有効な情報になりそうです。
町の標語を読む/”Reading the Signs” (p140)
私にとっても新しい示唆でしたが、著者は町の標語を読むことで、その社会でしていいこととしてはいけないことなどの価値基準や規範がわかると述べています。これは、面白いなと思いました。
例えば、インドのデリーには警察標語として次のものがあります。なぜ、当たり前のことをわざわざ掲示しているのか、それを考えると警察と市民の関係性に様々な問題が存在している、という可能性が疑われます。
そういえば、上海ではいたるところに「標準語(北京語)を話そう」という標語がありました。
標語だけではなく、同じように、町の看板を見て見るのも面白いかもしれません。アーメダバードの看板は、高等教育のもの、結婚式関連のものを多く見ます。スリランカのキャンディにはやたら英語学校の看板が出ていたのを思い出します。テレビCMや新聞広告などと合わせてみると、その地域で何が重要視されているか、何に出費が促されているかがわかります。
自分も消費者の一人なので、自らの判断や購買行動を冷静に分析してみる。(p168)
これは当たり前ですが、意外と分析側に回ることで、客観性を失うからといって見失いがちな視点です。しかし、自分の行動であっても一度分解してみると、観察すべきフレームの一部が抽出されることでしょう。
トーマス・ヴァレンティの普及理論(p84)
マーケティングでは、イノベーター(なんでもすぐ新しいものを試してみる人)からラガード(新しいものを最も受け入れないタイプの人)へと普及が進むという基礎理論があります。
ヴァレンティの普及理論では、必ずしもイノベーターからアーリーアダプター、フォロワーへと順を追って流れるとは限らず、親密な関係性の中でトレンドは伝播すると述べられています。
たとえば、自分の母親が新しいテクノロジーには全く興味がなくても、息子や娘がそれに強い関心を持ち同居していれば、影響を受ける可能性が高くなります。その場合、イノベーターからラガードまでの大きな溝は意外と簡単に超えることができます。
確かに、自分の身の回りの事例でも、この理論は本当だなと思うことが多くあります。また、仮にスマートファンに疎く設定方法がわからなくても、子供が全て設定して困ったときも解決してくれるのであれば、疎い人にだって使えるはずです。
最後に
日本語版は写真も入っていると聞いていますが、原著は論文のようにテキストのみなので一見読むのがしんどい気がします。それでも、実際冒頭から面白い事例を出して読者を飽きさせませんし、また方法自体も実践での応用がすぐ可能なものが多くおすすめの一冊だと思います。最後のページについているデザインリサーチ八原則だけでも、ちらっと見てみるとリサーチの助けになる要素がつまっています。
関連記事
-

-
アート、デザイン、サイエンス、ビジネスが交わる実験場。Godrej India Culture Lab。
インドで様々なビジネスを展開しているゴドレジには、異分野、異文化との交流
-

-
インド首相モディ氏、Twitterフォロワー820万人への発信とグローバル社会への影響力。Googleアドワーズで比較。
インド最大の英字新聞The Times of India(8月27日)にモディ氏のTwitt
-

-
信頼できる口コミをどうやって得るか。インド・グジャラート州で獣医を探しながら考えたこと。
Dr. Chirag Dave, PETS' CLINIC[/caption] インドで飼い
-

-
国立デザイン大学院(NID)卒の若手デザイナーの今。フラット化した世界におけるプロフェッショナルな働き方。
インド南部の大都市バンガロールで、グラフィックデザイナーとして働くMamataさん(写真左端
-

-
ジュガードという思考法。悪しき習慣かイノベーションか、スタンフォード大Dスクールにも事例あり。
インドにはJugaad(ジュガード)という言葉があります。 この言葉の定義をどうするか